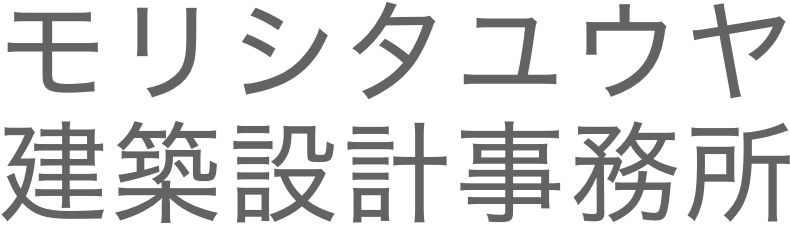眺望の権利
実は眺望・景観について、これを権利とする法律自体は存在していません。
では、眺望を楽しむことは「権利」として保証されていないのか?
海が見える高台など眺望を求めて建築・購入したにも関わらず、その眼前に
景色を遮るようにそびえ立つような建物をたてられた時、居住していた人の
立場からすれば、まさしく眺望が侵害されたとして「眺望権」の侵害を主張
したい所だと思います。
久々の投稿では、そんな権利の話を少し。
景観保護の考え方

冒頭で述べたように、眺望・景観についてこれを権利とする法律はありません。
しかしながら、景観保護についての意識の高まりを受けてH14年景観を阻害する建物の一部撤去
と損害賠償を認める判断が地裁でなされ、更にH18年には最高裁によって、「良好な景観に近接
する地域内に居住し、その恵沢を日常的に享受している者は、良好な景観が有する客観的な価値の
侵害に対して密接な利害関係を有するものというべきであり、これらの者が有する良好な景観の
恵沢を享受する利益は、法律上保護に値するものと解するのが相当である。」と述べ、景観利益が
法律上保護されることを認めるに至っています。
つまり、眺望を侵害する場合は不法行為にあたり得るとされたわけです。
しかしながら、景観保護についての意識の高まりを受けてH14年景観を阻害する建物の一部撤去
と損害賠償を認める判断が地裁でなされ、更にH18年には最高裁によって、「良好な景観に近接
する地域内に居住し、その恵沢を日常的に享受している者は、良好な景観が有する客観的な価値の
侵害に対して密接な利害関係を有するものというべきであり、これらの者が有する良好な景観の
恵沢を享受する利益は、法律上保護に値するものと解するのが相当である。」と述べ、景観利益が
法律上保護されることを認めるに至っています。
つまり、眺望を侵害する場合は不法行為にあたり得るとされたわけです。
法定判断
もっとも、眺望の妨げが何でもかんでも不法行為に該当する訳ではありません。
事実、上記の最高裁判決は土地の利用権者による建物の建築が第三者に対する関係において
良好な景観の恵沢を享受する利益に対する違法な侵害となるかどうかは、被侵害利益の性質
と内容、当該景観の所在地の地域環境、侵害行為の態様と程度、侵害の経過等を総合的に
考察すべきとし、つまるところ「事案毎に色々考えた上で判断する。」とされています。
その判断基準は厳しく、ある行為が景観利益に対する違法な侵害に当たるといえるためには、
少なくとも、その行為が刑罰法規や行政法規の規制に違反する侵害であるか、公序良俗違反
や権利の濫用に該当するものであるか?など、侵害行為の態様や程度の面において社会的に
容認される行為として相当性を欠くことが必要だとされています。
事実、上記の最高裁判決は土地の利用権者による建物の建築が第三者に対する関係において
良好な景観の恵沢を享受する利益に対する違法な侵害となるかどうかは、被侵害利益の性質
と内容、当該景観の所在地の地域環境、侵害行為の態様と程度、侵害の経過等を総合的に
考察すべきとし、つまるところ「事案毎に色々考えた上で判断する。」とされています。
その判断基準は厳しく、ある行為が景観利益に対する違法な侵害に当たるといえるためには、
少なくとも、その行為が刑罰法規や行政法規の規制に違反する侵害であるか、公序良俗違反
や権利の濫用に該当するものであるか?など、侵害行為の態様や程度の面において社会的に
容認される行為として相当性を欠くことが必要だとされています。
判例の一つ
令和元年の高等裁判所で、土地と建物を所有し、これを業務に使用している事業者が、その隣地に
マンションを建築した隣人に対し、自らの眺望権が侵害されたとして、不法行為に基づき損害賠償
請求をした事案があります。
この裁判例では、事業者が土地と建物を購入したときには両側の視界がひらけていたとしても、
それは周辺土地に事業者の所有建物より低層な建物しか存在しなかっただけで、そのような事情
をもって、事業者よりも高い建物の建築が制約されることにならない。との理由から事業者の
主張する眺望権もしくは法的に保護される利益に当たると評価することは困難であるとしました。
また裁判所は「いわゆる眺望の権利ないし利益は、建物の所有または占有と結びついた生活利益
であり、その建物の所有者あるいは占有者が持つことのできる利益ではなく、たまたま特定の場所
を占有することから事実上享受し得る利益に過ぎないものであり、周辺における客観的状況の変化
によって、変容し制約されるものと言わざるを得ないのであって、そのような変容、制約を排除
できる法的権利を当然に有するものということはできない。」としています。
マンションを建築した隣人に対し、自らの眺望権が侵害されたとして、不法行為に基づき損害賠償
請求をした事案があります。
この裁判例では、事業者が土地と建物を購入したときには両側の視界がひらけていたとしても、
それは周辺土地に事業者の所有建物より低層な建物しか存在しなかっただけで、そのような事情
をもって、事業者よりも高い建物の建築が制約されることにならない。との理由から事業者の
主張する眺望権もしくは法的に保護される利益に当たると評価することは困難であるとしました。
また裁判所は「いわゆる眺望の権利ないし利益は、建物の所有または占有と結びついた生活利益
であり、その建物の所有者あるいは占有者が持つことのできる利益ではなく、たまたま特定の場所
を占有することから事実上享受し得る利益に過ぎないものであり、周辺における客観的状況の変化
によって、変容し制約されるものと言わざるを得ないのであって、そのような変容、制約を排除
できる法的権利を当然に有するものということはできない。」としています。
眺望権の解釈
他方で、「このような眺望ないし景観に係る権利利益が法的におよそ保護されないものと解される
べきではなく、特定の場所がその場所からの眺望の点で格別の価値を持ち、このような眺望利益の
享受を一つの重要な目的としてその場所に建物が建設された場合のように、当該建物の所有者また
は占有者による眺望利益の享受が社会概念上からも独自の利益として承認せられるべき重要性を有
するものと認められる場合には、当該眺望利益は法的見地からも保護されるべき利益であるという
べき」と判示されました。
べきではなく、特定の場所がその場所からの眺望の点で格別の価値を持ち、このような眺望利益の
享受を一つの重要な目的としてその場所に建物が建設された場合のように、当該建物の所有者また
は占有者による眺望利益の享受が社会概念上からも独自の利益として承認せられるべき重要性を有
するものと認められる場合には、当該眺望利益は法的見地からも保護されるべき利益であるという
べき」と判示されました。
まとめ

裁判所の判例を基にしているため、いささか難しい言い回しとなっていますが、眺望権が法的に
認められるか否かは社会概念に照らし合わせて判断されると言うことになります。
もっとも、トラブルを防止するためにも眺望を期待されている地域では、特に近隣の方の理解を
得るように努めることがベターではあります。
一般的には己が住まいをベストな状態に置きたいものですが、景色を生活に取込める地域など
では皆が眺望を求めています。
同じ地域で同じものに惹かれた仲間通し互いを尊重しあい、その場所がより良く発展するため
にも場所に与える影響に責任をもつ必要があるのです。
他者の主張にも思いを馳せた設計を心掛ける必要があるでしょう。
認められるか否かは社会概念に照らし合わせて判断されると言うことになります。
もっとも、トラブルを防止するためにも眺望を期待されている地域では、特に近隣の方の理解を
得るように努めることがベターではあります。
一般的には己が住まいをベストな状態に置きたいものですが、景色を生活に取込める地域など
では皆が眺望を求めています。
同じ地域で同じものに惹かれた仲間通し互いを尊重しあい、その場所がより良く発展するため
にも場所に与える影響に責任をもつ必要があるのです。
他者の主張にも思いを馳せた設計を心掛ける必要があるでしょう。